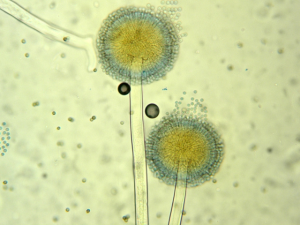〈カビコラム40〉カビ対策をする上での注意点①-カビ取り剤での事故トラブル
まもなく、湿度が高くジメジメとした梅雨の季節がやってきますね。
2025年の梅雨も、例年通り湿度が高く、地域によっては蒸し暑い日が多くなることが予想されます。

なぜ梅雨はカビの季節?カビが繁殖しやすい理由
そもそも、なぜ梅雨時期は特にカビが生えやすいのでしょうか?
カビが活発に活動し繁殖するには、主に「温度」「湿度」「栄養源」「酸素」の4つの条件が必要です。(※pH4〜6を好む)
一般的に、カビは[温度20~30℃][湿度70%以上]という環境で最も活発になります。
梅雨時期の日本の気候は、まさにこの条件を完璧に満たしてしまいます。
気温が上昇し始める上に、連日の雨で湿度が非常に高くなります。
さらに、この時期は窓を開けて換気することが難しくなりがちで、室内に湿気がこもりやすくなります。
空気中に浮遊するホコリや、浴室の石鹸カス、キッチンの油汚れなどは、カビにとっては格好の栄養源となります。
このように、梅雨時期はカビが最も好む高温多湿の環境が長く続くため、家中の様々な場所でカビが繁殖しやすくなるのです。

壁や天井、お風呂場やキッチン、クローゼットの中など、特に湿気が溜まりやすい場所には注意が必要です。
カビ取り剤での事故トラブルに注意!
カビ対策は、専門の業者に依頼する場合と、ご家庭で市販のカビ取り剤を使って対応されるケースがあります。
前回のコラムでも紹介しましたが、カビは種類によって色素を持つため、その色を消すために、利用するカビ取り剤は漂白作用が期待できる次亜塩素酸ナトリウムを含有する製品が多いのが現状です。
最近では、SNSなどを活用してカビの除去方法を学び、ご自身で作業を行う方が増えています。
しかし、カビ取り剤の取り扱いに関する注意点の認識が浅いまま作業をしてしまうと、思わぬ事故やトラブルが発生してしまうことがあります。
特に危険な「混ぜるな危険」
カビ取り剤、または漂白剤で起こる事故やトラブルの例としては、まず重大事故につながる可能性のある混触危険物質の混入による塩素ガスの発生が挙げられます。
他の液体を混ぜてはいけないのはもちろんですが、意外と注意を怠りがちなのが、酸性タイプの洗剤を使用した後に続けて塩素系洗剤を使用するといった、いわゆる「洗剤の重ねがけ」で起きてしまう混触です。

塩素ガスは刺激臭があり、目や鼻、喉などを刺激し、濃度によってはただちに生命に危険を及ぼす可能性のあるガスです。
空気より重いガスのため、気づかぬうちに低い場所に溜まり、屈んだ時に大量に吸い込んでしまう危険性があります。
他の洗剤と混じり合わないよう、使用する際は十分に注意する必要があります。
ガス吸引や身体への付着にも注意が必要
また、洗剤をスプレーする際に大量に吸い込んで気分が悪くなるケースや、高所で使用する際に目に入ってしまい痛みを伴うこと、皮膚に付着して薬傷を負うことなども報告されています。
これらの事例は、いずれも製品の使用上の注意事項が守られていないことが原因と考えられます。
安全な使用のために改めて確認すること
新型コロナウイルスの流行に伴い、漂白剤を除菌剤として利用するケースが増え、以前にも増して身近な存在になったと感じる方も多いでしょう。
1980年代からこの「混ぜるな危険」表示が義務付けられ、また換気や保護具(マスクやゴム手袋、ゴーグル等)の着用が呼びかけられていますが、今でも残念ながら事故やトラブルを耳にします。
取り扱いの際の注意事項を守ることで危険を回避できるにもかかわらず、一般的に販売されていることや、「いつも使っているから大丈夫」という慢心が、注意を疎かにさせてしまうのかもしれません。
カビ取り作業を行う場合は、洗剤に対する認識を改めて持ち直し、注意事項を把握した上で正しく使用することが非常に重要です。
梅雨入り前にしっかりとカビ対策を行い、安全にこの時期を乗り切りましょう。
事故事例(※厚生労働省_職場のあんぜんサイトより抜粋)
| 事例1 | 原因製品:次亜塩素酸ナトリウム / 硫酸 |
| 状況 | 被災者Aは、洗剤を補給するためトイレ内で、廊下に置かれていたタイルワックスをポリバケツに注ぎ入れたが量が少なかったので、タイルワックスの近くに置かれていた次亜塩素酸ソーダを追加したところ、ポリバケツから白煙が発生し、その白煙を吸入してしまい、気分が悪くなったので従業員用の控室で横になっていた。その様子を見たチーフは、事情を聞き、本社へ災害発生の報告を行った。その後、チーフは、災害が発生したトイレに赴き、白煙の発生したポリバケツに水を入れてトイレ内に数回に渡って流していたところ、気分が悪くなり被災者Aと共に病院に搬送された。 |
| 原因 | 洗剤として補給しようとしたタイルワックスは硫酸を10%含有しており、これに次亜塩素酸ソーダを加えたため、化学反応を起こし、塩素ガスが発生したものであること。容器に、含有成分、取扱上の注意事項が適切に表示されていなかったため、通常の清掃作業には使用しないタイルワックスや次亜塩素酸ソーダを通常使用する洗剤と思い込んで使用したこと。清掃員が、有害物を含有するタイルワックスなど洗剤の有害性に関する知識を有していなかったこと等。 |
| 症状 | いずれも塩素ガス中毒と診断され、Aは死亡した。 |
| 事例2 | 原因製品:塩素系漂白剤 / 塩酸 |
| 状況 | トイレの清掃をするため備付けの塩素系漂白剤(成分:次亜塩素酸ナトリウム等、液状、塩基性)をトイレの床にまき、その上に酸性洗剤(成分:塩酸9.5%)をまいて水をかけ、タワシで洗い始めた。 |
| 原因 | トイレ清掃の際、洗剤の性質、使用上の注意等を確認することなく、塩素系漂白剤と酸性洗剤を混ぜて使用したこと。トイレ内の換気が不十分であったこと。 |
| 症状 | しばらくすると、被災者が涙を流しながら咳き込み始め、苦しそうにしたため、同僚が車で病院へ連れて行ったところ「塩素ガス中毒」と診断1週間入院。 |